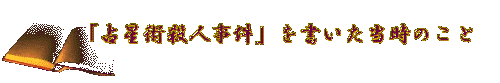
| (「本屋でぼくの本を見た」角川文庫に収録) 「占星術殺人事件」を書いた頃のことは、もうずいぶんあちこちで書いた気がする。この作品がぼくのデビュー作にして、未だに代表作と見なされているせいで、この種の文章を要求されることが多かったからである。けれど今こうしてあらためて筆をとって思案してみると、まだ語っていないこともある。 あの作品は、まことに単純な構造を持っていて、非常に大きなトリックをひとつ発見できたから、この一本の幹に、ちょうどクリスマストゥリーにあれこれ飾り付けをするようにしてさまざまなストーリィをまとわりつかせ、長編に仕立てあげたものだ。だからあのトリックさえ手にできたなら、誰でも拙作程度のミステリーに仕立てることはできたであろう。 そのトリックについては、未読の方のためにここで解体して述べることはしないが、あれは意表をつく解答を背後に隠し、非常に奇妙な設問として第三者につきつけることができるといった種類の謎だった。したがって口でくどくど語るより、むしろ長いストーリィとして、文章化して提出する方が効果が倍する性格のもので、すなわちクイズ自身が、自らを小説化するよう要求していた。こういうものをデビュー時に手にできたことは、まことに幸運というほかない。 あのトリックをぼくが発見できたのは、一九七六年か七年だった。 なぜ当時のぼくがこういうものを見つけられたかというと、あの頃の自分が、以前に増して「謎狂い」をしていたという事情がある。 自分が謎に目がない人間であるという自覚は子供の頃からあり、こういう趣味と、文章を書くことが好きというもうひとつの資質とをドッキングさせて推理小説家になるというごくあたりまえめいた帰結は、すでに小学校の時に一応の完成を見ていた。このあたりのことはあちこちで語った気がするから繰り返さないが、給食の時間が小学生作家の新作発表の文壇だった。するとあちこちの食事グループから負けじと推理作家が現れ、目黒区立東根小学校の一教室は、さながら新本格のムーヴメントの相似形が、時代に先駆けること三十年にしてすでに現れていた。 ぼくはそういう人間だったが、二十代の頃は作家になりたくなくて、むしろ活字から逃避しているようなありさまだった。このあたりの心理は自分でも不思議だが、思うに、できると解っている(と自分では思っていた)仕事をまた繰り返すことには、チャレンジ精神がかきたてられなかったのであろう。しかし謎への本能的な反応はいかんともしがたく、先述の通りあの頃、ちょっとしたクイズの類いにやけに敏感になっていた。 さてその理由を、これまでのエッセイで書き損じていたわけだが、それが何かといえば、あの頃一世を風靡していた「ナゾナゾブーム」である。 大半は他愛のないものだったが、なかには感心するものもあった。 刺激されて、さっそく自分でも作りはじめた。むろん自分なりにもっと高度なものを、という思いはあったから、図形のパズルのようなものも、当方の創作は含んで発展した。趣味が高じ、とうとうスポーツニッポンという新聞で、自作のナゾナゾのコーナーまで始めた。「遊びの博物誌」などという本を見つけてきて夢中になったのも、その頃のことだ。 ぼくがこういう状態にあったまさにその頃、「占星術殺人事件」をお読みの方はお解りであろう、例の「一万円札詐欺事件」のニュース報道があったのである。当方が「謎狂い」していなければ、こんな報道に食いつくこともしなかったに違いない。模倣されることを避けるため、「二十枚の一万円札を切りはなし、その一部を利用することでもう一枚余分にお札を作る詐欺です」というような言い方しか、確かアナウンサーはしなかったように思う。 二十枚のお札から一部ずつを二十片集め、テープで貼り合わせたひどい札が使用できるはずもない。これはもっとスマートな詐欺のはずである。 この意味不明のコメントを、自分に出題されたクイズと受けとめ、紙とハサミを持ってきてコタツの上で挑戦に応じた。さんざんトレーニングされ、クリアになった頭だからすぐに状況は把握でき、なるほどとしばらく感心した。そのまま何週間も放っておいたら、ベッドの中で突然これが小説になったので、びっくりしてとび起きた。 そしてやむなく、自分にはこれしかできないらしいあの懷かしい小学校時代の仕事に、渋々戻ることにしたのだった。 (’94・5) |