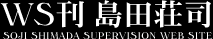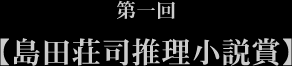
![]()
数学オリンピックにおいて、中国はここ10数年、優勝を続けています。2007年度の第4回国際ジュニア・サイエンス・オリンピアードにおいては、台湾の高校生たちが優勝しました。
これは20世紀の百年間をかけ、数学や物理学のセンスで成長をはたしてきた「本格ミステリー」という新興の文学ジャンルへの、華文文化圏の若者の適正を示すものと私は考えています。これらコンペティションへの参戦に必要なロジカルな思考力に、文学的なイマジネーションの力が加われば、これまで日本の才能が中心になって発展させてきたこの文学ジャンルを、華文の才能が替わって担える時代も来ると、私には感じられます。
ゆえに、華文で書かれた本格ミステリー小説を対象とした新賞の設立は、現時点が好機であると考えて、大いに期待しています。また私がその最終の選考委員を依頼されたことに、大きな誇りと、感謝の念を抱いています。
この賞は、華文が書ける新しい才能ならば、地球上の誰もが平等に応募できる、画期的なものです。
そして受賞作品は、台湾では皇冠集団が繁体字で即時出版しますが、中国では当代世界出版社・青馬文化(中国)有限公司が簡体字で同時に出版、日本では最大の老舗、文芸春秋社が日本語に翻訳して刊行を担当、タイでは南美出版社( Nanmeebooks )がタイ語に翻訳して、刊行します。
四出版社は、本格ミステリー文化の豊饒を目指すアジアの同胞として一体となり、同時刊行を目指します。成功裏に回が重ねられるなら、出版は将来四出版社に留まらず、ミステリーをキーワードに、アジアの全域に広がってひとつに結んでいく、壮大な夢をはらむ企画です。
しかしこの賞の設置を聞いて、華文文化圏の方々が抱いたであろう大きな疑問や不安に、私自身推察が及びます。以下でこの疑問に答え、この画期的な新賞において、定着を目指したい新しい選考の方法について、説明したいと考えます。そして外国人の私が、何故こうした賞の最終選考委員が可能と考えたか、さらに言えば、時として外国人であることがむしろ有利に働くと考えた理由を、ご説明いたします。
華文を読めない私が、華文で書かれた小説の審査員をすることは可能なのか、という疑問は当然です。ここからこの賞における島田荘司もまた、過去に多くの例があった名前貸しであり、実質上の審査委員は、台湾人の下選考者になるに違いないという推察は妥当です。
通常の小説の賞では、よく流れる美しい文章を繰り出す力や、登場人物の思いや行動を的確に描写する力、これらを使って面白く小説を読ませていく技量、背後にあるその作家の思想性や文学性も重大ですから、そのためには、選ばれている題材もまた評価の対象です。またこうした小説は、読む者の生活環境によって、有効性や重要度あいに違いが生じますから快活水準や環境を考えずに世界を舞台にすることは、むずかしい面もあります。
審査委員は、応募作品によって、書き手の持つこれらの力をはかります。あるいはこの作品単体に現れた、そうした技量の痕跡や、達成の度合いを評価します。このような審査ならば、外国語圏の人間が、評価に加わるべきではありません。
こうしたことを考える時、私には、いつも気づかされることがあります。それは、本格ミステリーそのものの将来にもかかわる、非常に重大な問題です。日本には、「江戸川乱歩賞」という推理小説界最大の賞がありますが、新本格派と呼ばれ、現在日本の本格フィールドの中核を担っている実力派の作家たちが、過去全員この賞を落選するという出来事がありました。落選のみならず、候補作になった作家さえ出ませんでした。台湾にも、過去似たケースがあったと聞いています。
こうしたことは、大変ゆゆしい問題と私はとらえます。過去の日本の本格を含むミステリーの賞の選考発想には、根本的な誤りがあったといわざるを得ません。この誤りを端的に述べれば、本格を含むミステリーの小説賞もまた、先述したような、通常の小説賞の選考と、まったく同じ物差しをあててはかられたからだ、と言えます。
この教訓から導かれる重大な事実は、「本格ミステリー」の賞においては、通常の小説賞において好評価を誘導するであろう技量群のほかに、さらにもう一段上位の要素、本格ミステリーという小説群においてのみ有効な、特殊な技能が存在する、ということです。そして華文によるミステリー文学賞こそは、本格や、本格に寄ったミステリーの、優秀作品を求めるものです。
この特殊な技能とは何かを説明するには、「本格ミステリー」とはどんな小説のことかを説明する必要があります。ごく簡単に述べれば、「謎」→「解決」という背骨を、物語の底部に沈めた物語のことです。そしてこの「解決」を導く方法に, 推理をはじめとする論理思考を大いに活用する小説のことです。
この時に現れる論理性が、一定量以上に緻密で高度なものを、「本格」と呼びます。この「一定量」の線引きラインは、時代や個人によって変化し、常に議論を誘導しますが、
大多数が同意する本格の領域というものは、上層に必ず存在しています。
しかし、これだけの要素では、これはよい小説にならないかもしれませんから、この骨組みに、さまざまな肉付けを施します。もともとの背骨が細く、まとわされた肉の方が美味ならば、「謎」→「解決」の背骨は底部深くに埋もれてしまって、読者たちに気づかれずにすんでしまうかもしれません。こうした小説は、本格度は高くないことになりますが、小説として必ずしも評価が低くなるとは限りません。華文のミステリー文学賞においても、こうした作が落選するとは限りません。
すなわち、本格ミステリーの作品とは,程度の差はありますが、読み手の驚きをもくろんだ、「人工的な装置」の別名なのです。たとえ非常にリアルな道具立てが用いられていても、前段や結部の驚きが大きいなら、その作は、必ず作者の意図的な演出の産物であるはずです。
この人工性や、驚きの演出という本格ミステリーに特有の発想が、幼いものとみなされ、純文学系の作例より、芸術性や高級性が低いという判断の理由になりがちです。しかしそうした感想は、別所由来の要素から発生していることが多いのです。すなわち「人工的」を作者自らが開き直って軽く考えてしまい、無数にある前例の借り物ですませたり、読者を楽しませる方法を、定番借用で手軽にすませてしまって、ゆえに驚きも定番にしてしまい, 高度経済成長時代、日本で大いによしとされた先人模倣の行儀が、こうした態度を道徳的と誤認させて、本格ミステリーを非創作と誤解させました。
しかし、純文系、私小説系の、きわめてノンフィクションに近い小説形態でさえ、読者に面白く読ませるには作者の計算や演出の参加が必要になります。また本格ミステリーが結部でもくろむ驚きにも、人生を生きるうえできわめて有意義な、深い感動や教訓を含ませることも可能です。私個人の経験では、論理思考の習慣獲得は、人生への処し方や、民族的な問題点を解体する上でも有効なものでした。宗教家が至上の高価値と信じる聖なる物語も、ミステリー小説と評価することは可能ですし、日本の近代文学の原点に位置する名作群も,その一部をミステリーとして楽しむことは可能です。
いずれにしても、「本格ミステリー」が驚きをもくろむ人工的な装置であるなら、文章力も、人間描写力も、そうしたメカニズムの一パーツであり、最重要なものではなくなってきます。読者に未体験の驚きを提供せんとし、読書中の彼らの抱く思いを都度予測しながら、装置の全体を俯瞰して驚きに導いていく、そうした迷宮を設計していく能力こそは、最大限に重要となってきます。
そしてこれが賞に応募された作例であるなら、この設計力こそが、最大の評価対象となってくるはずです。先に述べた、文章力よりも上位のものとは、この設計力です。文章が手段であるということは、後半の驚きの要請によっては、あえて非文学的な、稚拙と見えるまでの文章を用いる演出もあり得ますし、人物の描写力も、あえて未熟なものにしておかないと、先での読者の驚きが減衰するケースはあり得ます。これこそは、本格のミステリー小説に限った創作技術といえるものです。
そういう事情なら、こうした見せかけ上の稚拙さに惑わされない強固な評価の軸を、審査委員は持つ必要がありますし、構造体の設計意図への洞察力こそは、最大限に要求される適性ということになります。
構造体設計力への評価であるなら、外国人であることは必ずしもハンディとはならず、時として有利に、より客観的に働くことはあり得ます。また日本の新人の本格作品の評価と選出を、20年近く続けてきた経験は、有効に生かせるものと信じています。
そのため、応募者には応募作にあらすじを添付してもらい、また述べたような構造設計意図ともいうべきレポート、これは自作をほかの作例と隔てると信じる、独自の優れた要素、と言ってもよいのですが、これを述べたレポートを、あわせて提出してもらいます。 下選考の人たちによってこれらはさらに書き足され、より詳しい説明となって私のもとに届けられます。が、それでも私は、これらあらすじと設計レポートのみで審査は行わないつもりでいます。あくまで和訳文を読むことを優先し、構造設計レポートを目にするのは、そうしたのちにしたいと考えています。
しかし完全な和訳文は、当初は候補作品各々の一部分となり、全体は粗い日本語となるかもしれません。残念なことですが、もしも賞の回数が重ねられるなら、近い将来、優れたコンピューター翻訳の登場により、候補作品すべての完全な和訳文を、短時間で作成できる時代も到来するでしょう。
現在、本格ミステリー創作の動きは、日本を出て、アジア全域に広がりつつあります。
私自身は全力をあげてこれに協力し、現在私に廻ってきているらしい使命を、すっかりはたしたいものと考えています。
2008年2月 島田荘司